自分ってなんなのでしょうか?
僕はなぜ、これが出来て、これができないと思っているんだろう?
自分の殻を破れるかな?
そうだ、養老孟子先生の本で勉強してみよう!
今回のキーワードはベクトルと自信です。
自信が付く3つのヒント。
「自分」の壁
まず今回読んだのは2014年出版の「自分」の壁。
養老孟子先生の「壁」シリーズの1つです。
見開きにはこう書いてあります。
「自分探し」なんてムダなこと。「本当の自分」を探すよりも、「本物の自信」を育てたほうがいい。
脳、人生、医療、死、情報、仕事など、あらゆるテーマについて、頭の中にある「壁」を超えたときに、新たな思考の次元が見えてくる。
「自分とは地図の中の矢印である」「自分以外の存在を意識せよ」「仕事とは厄介な状況ごと背負うこと」
――『バカの壁』から一一年、最初から最後まで目からウロコの指摘が詰った一冊。
累計580万部突破、「壁」シリーズの最新刊!
「自分探し」はムダ、自信を付けなさいとこう仰っています。養老先生らしいですね。
養老先生は東京大学名誉教授、医学博士、解剖学者として非常にユニークな視点を持っておられます。虫好きでわりあいクールに人間の事も考えてたりします。
頭の構造がだんぜん僕とは違います。
他の著書で「人間の脳を人間の脳で理解しようとする限り限界がある」というような事を言っていたんですけど僕のようなド素人でも説得のお言葉。
結局、「自分」だって「自分」が理解しようとしたって限界があるように思います。全く考えないよりは考えたほうが良いんでしょうけど、それより自信を付けなさいと。

養老先生いわく「自分」というものは脳と意識が境界線をつくっているそうですね。ここからここまでが自分と。そして自分側を「えこひいきをする」そうです。
脳のその境界線を引く機能がなくなれば自分を液体のように感じ、全部が自分になってしまい至福の状態になるとも言っています。怖いけど興味深いです。
自分のツバですら、いったん自分という領域から出てしまうと「えこひいき」出来なくなる、汚いものになってしまうと言っていますが確かにその通りですね。
とにかく、自分とは意識が勝手に作り上げているものなのでそんなに肩に力を入れずに「自分」とは「肉体の壺」、「現在位置の矢印」程度の認識で良いのではないかという事を仰っています。
そういったクールな視点で「自分」の壁というものを考えてみると、そもそも「自分、自分」とこだわる必要すらないものかもしれませんね。
大事なのはどう自信を身に付けるかって事です。信頼を自分に置くか、他人に置くかって事。
では僕なりに本からもらった自信を付けるヒントをまとめます。
ヒント1、自然を一日10分見る。
自分は状況の中の一部、自然の中の一部として捉えなさいと書いています。
山も川も風も自分の思い通りにはいきません。あなたは山を動かそうとしていませんか?
他人の心を思い通りに動かそうとしていませんか?
出来る事もあります。よく観察するんです。
広い視点を持ちよく観察すれば自分の「ベクトル」もおのずと定まっていきそうです。ベクトルがわかればあとは進むだけですね。なるべくシンプルに考えると良いかもしれませんね。
何に興味がありますか?ストレスなくやっているけど他人にマネできない事はありませんか?
養老先生は顕微鏡が高性能になって良い事もあれば悪いこともあると言っていました。余計なものまで見えてくると全体像がぼやける事があるんですね。
職場などでも毎日同じ顔と同じような仕事では煮詰まってしまいます。なるべく自然を眺めたりして視野を広くしましょうね。時には大きなものに身をゆだねるのも悪くないかもしれません。

自然
養老先生曰く、自然を見ると頭が良くなるそうです。最近、近視の子供も多いと聞きます。意識的に自然を見るとたくさんのご褒美があります。
養老先生は離島に住めば良いなんて言ってますけど、可能ならば住みたいですね!
キャンプが流行っていますが週に一日で良いから離島で過ごせたらストレスも大分軽減されるでしょうね。自然の中で深呼吸してリラックス。
ヒント2、面倒を引き受ける
面倒な場面で逃げるとその時は良いんですけど、また同じような面倒が来た時にまた逃げなくてはいけなくなります。
そうすると「なんだか面倒が呼んでも無いのに来る状態」に陥りやすいという事です。結局、性格や生き方がその面倒な状況を作り出している場合、逃げるのは長い目で見て得策じゃないかもしれません。
楽しようとせずに、「自分の胃袋」=自分の対応できる範囲で、面倒な状況に立ち向かっていくと自信に繋がると先生は言います。トライアンドエラーですね。

困難
多少の面倒には立ち向かい、挑戦を続けましょう!
ヒント3、自分は自分だけのものではない
人間も環境の一部だと養老先生は仰っています。
自分は自分だけのように思えますがみんなのものかもしれません。自分を粗末にしたら周りの人が悲しむっていうのもあるんでしょうけど、細菌やウイルスだって自分の中に住み着いててあなたを頼りにしているんです。
ウイルスのために明日も元気に生きてください!なんて事は言いませんけど運命共同体の生物もいるんですね。自分が思うより自分をあてにしてる生物がいるって事です。
たまには自分の中にいるウイルスに「まあ、いっちょ楽しくやってくれよ」と、話しかけましょうよ!
視点を変え、自分を大切にして自分から良くなっていけば周りの環境にも良いって事です。ボランティアだと思って自分を大事にすれば体内の細菌から思わぬプレゼントがもらえるかもしれませんね。

休憩
栄養、休息、足りていますか?
自分を大事にして、体調も絶好調なら自信に繋がります!
感想
養老 孟司(ようろう たけし、1937年11月11日 – )は、日本の医学博士、解剖学者。東京大学名誉教授。神奈川県鎌倉市出身。
2003年に出版されたバカの壁は419万部を記録し、戦後日本の歴代ベストセラー4位となった。
(引用・抜粋:Wikipedia)
養老先生は80歳を超えたユニークな視点を持つ東京大学名誉教授の賢人です。本も養老先生の頭の中を覗ける内容となっています。
今回「自分」の壁、というタイトルですが自己啓発というよりは、養老先生のユニークな視点から世界を楽しむような本だと思います。
政治、いじめ、生と死、医療問題など多くのお題について面白い持論を展開されています。参勤交代をせよ、いじめはなくならないので逃げ道をつくってやるべきだ、などなるほどなって意見も多いですね。
特に情報過多の世の中でメタメッセージに気を付けよという養老先生の言葉は響きました。
ニュース番組などで情報がたくさん飛び込んでくるとメタメッセージのみが残り、それが単純化し、「○○が嫌い」など漠然とした感情が形成されることがあるそうです。確かに僕も実際に被害にあったことも無いのに「○○が嫌い」といった感情を持つ事があります。自分の感情をきちんと見つめていきたいですね。
また養老先生自身も私は元々ずれているってお話しされているので、なんとなく生きづらさを感じている方にも勇気を与えてくれると思います。そもそも私はど真ん中に生きているよって言う人に会ったことないし、そんな事言っている人がいたら、この人こそずれているなって思いますよね。
ずれていたってこのように立派な本を出せます。
ずれながら人生のベクトルをなんとか自分なりにまっすぐにしていけば良いのではないでしょうか?
今回の本
【書籍名】「自分」の壁
【著者名】養老孟子
【出版社】新潮社
【出版日】2014/6/20
そもそも脳や意識が「自分」というものを作っているとしたら「自分の壁」っていうのもそもそも脳が作った抽象的な概念なだけかもしれません。
だから「自分の壁」ってやつは「自分の小さな常識」。壊すとか壊さないとか小さなことです。
「私は○○ができない」「○○が苦手」っていうのも事実じゃない可能性だってあります。
自信は挑戦を繰り返していくしか身につかないとの事ですので無理のない範囲で挑戦を繰り返していきましょう!
先日書いたブログで「失敗は最高の贈り物なんだ。」って話がありましたけど、挑戦する事には人生を大きく前進させる効果がありますね。
疲れた時には自然を見つめて自分の立ち位置を確かめ、進むべきベクトルをまた確認して前に進みましょう。
今回のキーワードはベクトルと自信です。
養老先生は他にも『バカの壁』『死の壁』『超バカの壁』など多数執筆しておられます。本自体は読みやすいので気が向いたらお手に取ってくださいね。
チャレンジ、チャレンジ!
ランキング参加しています。お願いします!
![]() 一緒にブログをやりませんか?ブログをやるならエックスサーバ!
一緒にブログをやりませんか?ブログをやるならエックスサーバ!![]() どんどん人生は良くなります。頑張りましょう!
どんどん人生は良くなります。頑張りましょう!
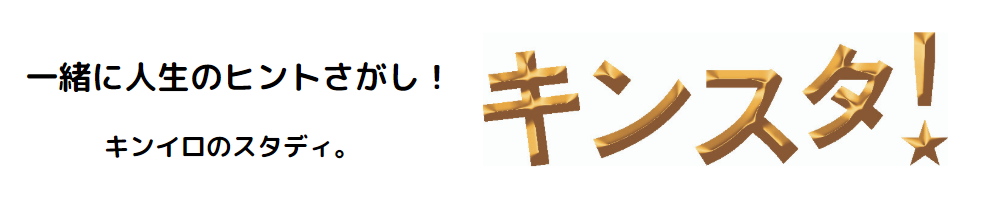
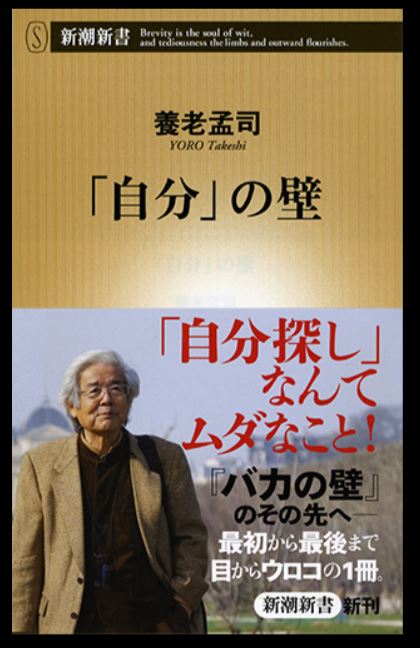
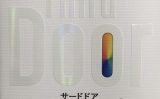


コメント