こんにちは!金時です。

今日も悩んでいますか?
前回、姜尚中先生の著書『悩む力』をまとめました。
今回は、続編『続・悩む力』!
さらに読み進めて「非常事態の今」を生き抜くヒントを得たいと思います。
『悩む』とは終わりなき青春。
悩みをエネルギーに変えろ!
もはや、「悩めるものは幸いなり」。
おめでとう!ようこそ、こちら側へ!
悩んで当たり前、困難こそ人生。
年を重ねてますます横着に、悩みながら永遠の青春の中を生きる!
今までの当たり前の世界は「流動化」してしまった。
まだ古い「幸福論」にしばられたままではないですか?
前回の「悩む力」は以下にまとめています。
ご興味のある方はぜひお目を通してください。
今回、著者は実用主義を世に知らしめたアメリカの心理学者のウィリアムズ・ジェイムズの言葉を引用し、こう語ります。
「”病める精神”。悲劇に見舞われて不幸な状態にある人ほど、宇宙に存在する深い真理を垣間見ることができる」
深い闇の中に入った時こそ、深い真理を垣間見るチャンスかもしれない。
時代は便利になりました。
今すぐ世界一の有名人にSNSを通じてメッセージを送れる時代になりましたね。
それで幸福になりましたか?
そう、結局科学も万能じゃない。
そして「カジノ化」した資本主義。

勝者は少ない。
生活に息苦しさを感じる。
心は満たされず、インターネットを探しても答えなど存在しない。
心細い我々の存在。
確かなもの。それは「悩んでいる自分」。
宇宙に漂う、はかなくも折れない「考える葦(あし)」。
その「悩んでいる自分」の中に、新しい幸福の足がかりを見つけるヒントがあるかもしれません。
というわけで『続・悩む力』から人生の生きるキーワードを6つピックアップしてみました。
姜尚中『続・悩む力』から学ぶ非常時に生きる6つのヒント。
1. 古びた『幸福感』を追い求めることの不幸。
資本主義社会は国境を軽々と超える企業を誕生させました。
全世界に影響を与える輝かしい経営者たち。
そこには少ない勝者と多くの敗者たち。
勝者は英雄として人が集まり、敗者は人格まで否定され、競技場の外へ駆逐される。
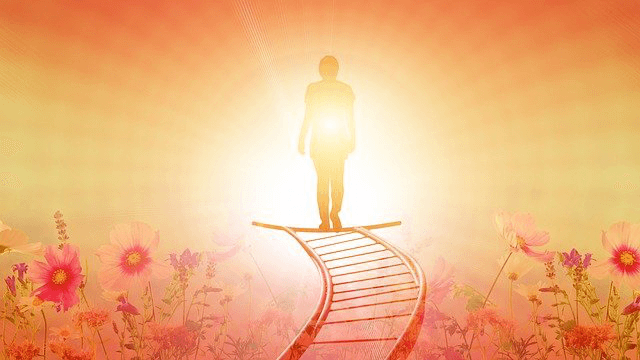
芥川龍之介『蜘蛛の糸』のようですね。
細い糸をたどり、一握りの勝者を目指し蜘蛛の糸を昇り、天上の世界に行こうとする。
私も『蜘蛛の糸』のカンダタと変わらないのかもしれない。
とにかく資本主義が提示している古い「幸福論」は5つの人生の悩みへと手を伸ばすことになります。
・愛
・家族
・自我の突出(承認欲求)
・世界への絶望(生きる意味の追求)
健全に幸福を求めるのは良いと思います。
しかし、古びた「幸福感」は新しい悩みを生みます。
それは足りないことが前提だから。
これら5つを完璧に満たすことは不可能です。
自分から苦しみをしょい込むことと一緒です。
もともと足りないことや不安を前提に、「幸福」を追い求めている限り、手に入れても、手に入れても足りないでしょう。
「お金と愛情と仕事とプライベートがぜんぶそこそこ満たされていて、しかも、その状態をキープしたまま、老後まで人生をまっとうできる。これは平凡なことでしょうか」
著者はこう問いかけました。
そうです。もはや古びた「幸福感」は”そこそこ”満たすのだって難しい。
著者はそこそこ満たしている人だって特権階級にいるとまで言います。ハードルが高い。
資本社会が作った足りないものを追いかける「幸福」を追いかけるのはヤメにしましょう。
では、本当に心を満たすものはなんでしょう?
著書に引用されている『夜と霧』で有名なオーストラリアの精神科医V・E・フランクルの言葉にヒントを得ました。
「人生に問うのではなく、人生が投げかけてくる「問い」に答える」
「どうやったら幸福になれるのか?」とあなたは問います。
しかし、逆なのです。人生があなたに問うているのです。
人生はいつもあなたにたずねてます。
「さあ、お前だったらどうする?」と。

そして人生があなたに要求してきます。
「お前に何ができる?」と。
運命に、人生にあなたが「応答」するのです。
人生にイエスと言いましょう。
自分の価値を感じたければ、他者貢献をせよ、と心理学者アドラーは言います。
ちっぽけだけど「かけがえのないあなた」。
この世界にあなたのアクションを待っている人がいます。
あなたにしか笑顔にできない人がいます。
運命を受け入れ、使命を全うしましょう。
困難や孤独だってあるでしょう、生きてるんですから。
でも、あなたを必要としている人は必ずいます。
目を見開いて、耳を研ぎ澄ませてください。
幸福への道はすでに目の前にあります。
丁寧に健康に自分の人生を歩めばそれでいい。
自分の価値を信じる。
2.己を忘れるべし。
突然「悩む力」とは逆説的になりますが、著者は漱石の創作メモ「断片」の一節を引用します。
天下に何が薬になると云うて己を忘るるより鷹揚なる事なし無我の境より歓喜なし。カノ芸術の作品の尚きは一瞬の間なりとも恍惚として己を遺失して、自他の区別を忘れしむるが故なり。
人一倍鋭い神経、優れた知性で心をすり減らし胃潰瘍になり血を吐き、自意識と徹底的に向き合った漱石はついに「自分を忘れろ」と言います。
どんな薬を飲むよりも自分を忘れ、無我の境地に至ればこの上ない歓喜がある、と。
漱石なりに悩み抜き、禅のような境地に達したようです。
徹底的に自我にこだわり、最後に「自我を手放す」。
漱石の域に達するのは難しいですが、
生活の中に座禅や瞑想を取り入れてみましょう。
自分を手放す時間を作るのです。
瞑想には、リラックス効果やストレス耐性がつくと言われています。
心を使い、また開放するといった訓練で、弾力性が増して新しいアプローチが生まれてくると思います。
急がば回れ。
静と動、陰と陽、天と地。
全ては振り子のように逆に大きく揺れてこそ、大きな円を描きます。
3.吾輩は過去である。
著者は漱石の「吾輩は猫である」をもじってこう言います、
「吾輩は過去である」と。
ウケ狙いではありません、おそらく、たぶん。
V・E・フランクルは、人間は「一回性」と「唯一性」の中で生きていると述べます。
・唯一性…その人がこの世にたった一人しかいないこと
です。人間らしさの根本であり、当たり前すぎて普段あまり深く考えないですよね。
しかし著者はよりよく生きるなら「一回性」と「唯一性」を取り返せ、といいます。
そのためには、未来ではなく過去を大事にする。
「今を大切に生きて、良い過去を作れ」と。
過去は、あなただけの完全オリジナル。
未来志向ならぬ、過去志向。
「この瞬間はきっと一生の思い出になる」と思って、その瞬間を愛おしく生きる時ってありますよね?
それは「この瞬間は二度とない」「私だけの体験」という「一回性」と「唯一性」を体験している瞬間だと思います。
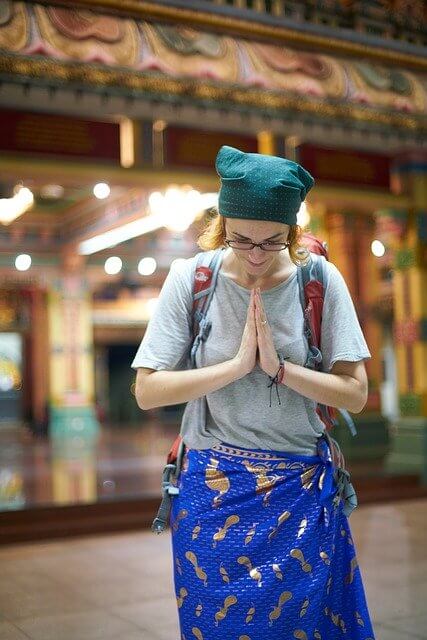
感謝!
その満ち足りたい瞬間には、不思議と未来からの自分の視点も感じるはずです。
「良き過去」を作ろうとした時、過去・現在・未来の視点が同時に働きます。
だから、吾輩は過去である。
猫にはなれませんが、今を懸命に生き、良き過去を作り、一度きりの人生を生きてください。
未来は誰にもわかりません。
しかし、この瞬間のあなたを大切にして、確かな過去を作れば、きっと素晴らしい未来に続いていくと思います。
4.二度生まれ。
前作『悩む力』に出てきたキーワード、福沢諭吉の「一身にして二生を経る」。
「恰(あたか)も一身にして二生を経るが如く、一人にして両身あるが如し」
激動の時代、一度の人生で2つ、3つの生があるがごとく変化が起こります。
こんな現代に、そのまま生まれて、そのまま死ぬっていうほうが難しいですよね。
学び続けて、変化を楽しんで生き抜いていく。
ならば進んで自分から、人生を2つ、3つ生きるつもりで果敢に生きてやりましょう。

進化
今回の『続・悩む力』ではジェイムズの「二度生まれ」という言葉を引用します。
意味合いは異なりますが、似ています。
そう、著者は続けざまに「一度の人生で二度生きる」にこだわります。
ジェイムズの「二度生まれ」というのは、
「健全な心」で普通に一生を終える「一度生まれ」、
「病める魂」で二度目の生を生き直す「二度目生まれ」の人生のほうが尊い。

一度生まれの人の宗教は「一種の直線的なもの」であり、「一階建てのもの」である。
これに対して、二度生まれの人の宗教は「二階建ての神秘」である。
といっています。病める魂から生まれ変わった「二度生きる」人は、人生の神秘に触れられる。
著者は、漱石やウェバー、ジェイムズ、フランクルらは誰もが、死地から立ち上がったと言います。
逆境から立ち上がって、初めて常人と異なる世界を描き、非凡なる才能を手にしたと。
序文にも書いたようにジェイムズの言葉をもう一度引用します。
「”病める精神”。悲劇に見舞われて不幸な状態にある人ほど、
宇宙に存在する深い真理を垣間見ることができる」
悩み抜き人生に打ちのめされ、何もかも失った時に、軸となる本当の自分に出会えるのかもしれません。
歴史を見れば悲惨な運命を受け入れ、不屈の魂で立ち上がり偉業を達成した巨人たちを発見できると思います。
でも偉人にならなくてもいいんですよ。
弱くても、不幸でも2度でも3度でも生きるつもりで何度でも立ち上がりましょう。
どんな運命だって受け入れてやりましょう!
うまくいかなくたって良いじゃない。
なかなかうまくいかないところが面白い!
5.「まじめ」に共鳴する。
こちらも前作『悩む力』に出てきた「まじめたれ」の延長となっているようです。
アドラー心理学では「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と言い切っています。

現在、家族や共同体、国、今までの人々のつながりを支えていたものが実体を失い、我々はまた「個人」として宇宙に投げ返されてしまいました。
その共同体感覚が断ち切られた苦しみは深い。
著者は、テイラーの「個人的な共鳴(パーソナル・レゾナンス)」という新しい共通言語が新しい人々のつながりの手がかりになると言います。
人が互いに共鳴し、境界を超えて投げ出しあい、信じあえるような世界を再構築する。
お互いの「魂を共鳴」させる。
そのためには、一人の人間と真剣に向き合う「まじめ」さが必要だと著者は言います。
まっすぐ人に向き合う「まじめ」さから、「魂の共鳴」をしてこの世界と確かなつながりを手にできると思います。
その共鳴が大きくなり、それが「うねり」になる時、我々は新しいつながりを発見できると思います。
6.人間の3つの価値。
V・E・フランクルは人間の価値を3つに分類しています。
・経験
・態度
ひとつひとつ見ていきましょう。
創造
新商品を開発する、新しい業務アイデアを出す。新しい言葉や絵画を「クリエイト」する。新しいものを創造することこそ、人間の真価です。
創造というと難しそうですが、前作『悩む力』で扱ったブリコラージュ的な生き方はどうでしょうか?
「その場にある全ての知恵や物質を寄せ集めて、自分の身の丈に合わせた知性をつなげていく」

スティーブ・ジョブス的にいうと「点と点をつなげる」作業です。
その場にあるものをつなげて新しい価値を作っていくんです。
知恵と知性のジャムセッションです。
あなたの好奇心、そして知恵、全てが「創造」につながり、あなたの価値を高めてくれるのです。
経験
「創造」の元になるもの、それは経験です。
さきほどのジョブズの言葉を借りると「点」を打つ作業になると思います。
新しく教室に通う、ボランティアをする、見知らぬ国を旅する。
なんでもOK。
やったことがないことにチャレンジし、知らない世界に飛び込む。
あなたの経験は、あなただけの唯一無二のもの。
行動があなたの人生を広げてくれます。
経験と行動があなたを確かな存在にしてくれるものだと思います。
態度
V・E・フランクルは人間の価値の中でもっとも「態度」を重視しました。
現在の社会においてもっとも難しいのは、この「態度」ではないでしょうか?と著者は問います。
どこを見ても取るべき「態度」に失敗した人は探さなくても毎日のように出てきます。
苦境に立った時、どのような態度を取るかが最もその人を浮き彫りにさせます。
むしろ、人生最後の瞬間であっても、きちんとした態度で迎れば、人生最後の日に幸福になることだってできます。
すべてがひどい人生だとしても価値や尊厳を生むことができます。
今の社会構造や資本主義構造、勝ちか負けか、意味があるかないか、その対極に人間の「態度」はあると著者はいいます。
さあ、どうふるまいますか?
その「態度」があなたの価値となります。
まず背筋を伸ばし、まっすぐ前を見る。
まとめ
今回は姜尚中さんの『悩む力』の続編『続・悩む力』から学んだ生きるヒントを自分なりにまとめました。
2011年の東日本大震災の翌年に発行された本ですが、あの時の「非常事態」と今の「非常事態」。
もはや非常が日常になりつつあります。
とにかく時間だけはあっという間に過ぎていきます。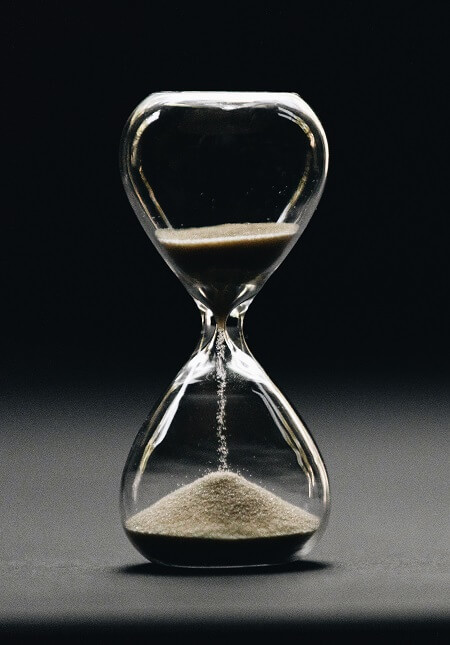
困難な状況でどうやったら前を向く力を手に入れられるのか?
今こそ読み返してほしい本だと思います。
3時間もあれば読了できますが、過去の知の巨人たちも同じように悩み苦しんだ例を多く知ることができます。「悩む」現代の我々にも活力をくれるヒントになる一冊だと思います。
『悩む力』は前に進むエネルギーになる。
みんな同じように悩んでその命を輝かせてきました。
いつまでも若々しくみずみずしく悩んでください。
最後に、この本の一節にあるジェイムズの『宗教的経験の諸相』から「個性は感情に基づいている」という言葉が面白いと思いました。
個性とは結局は「感情」じゃないかと。
悩み、苦しんだ末に獲得した「豊かな感情こそがその人の個性」ではないかと。
今生きていることが自分に出会う瞬間、瞬間なのです。
これからも「非常事態」や想像だにできない出来事が起こっていくでしょう。
その度に我々も何度でも立ち上がり、この不条理な世界を笑ってやりましょう。
「二度生まれ」でも「三度生まれ」でも生きている限り、この人生を味わい、見届けてやりましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
きっと我々は生き抜ける。
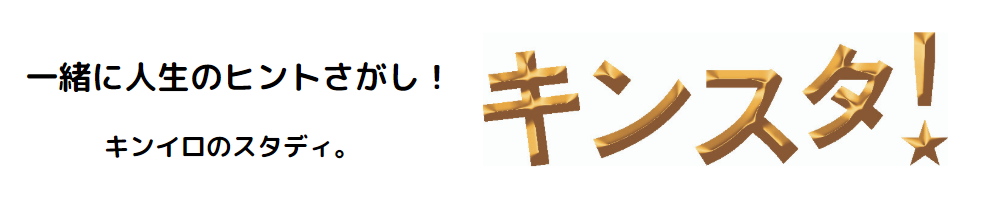
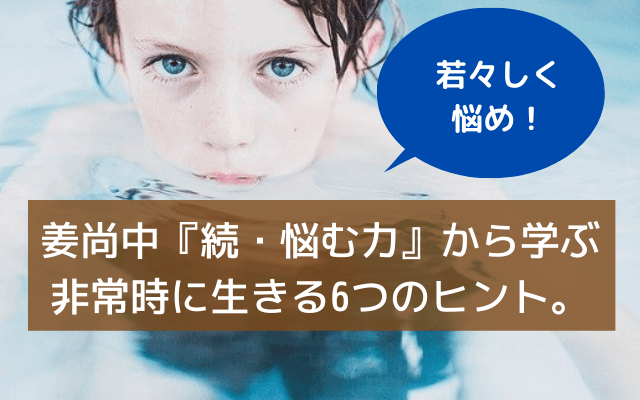



コメント