みんな大好き、横浜!アーンパンチ!

2019年、リニューアルしたアンパンマンミュージアム
今回は「ヨコハマ歩きが10倍楽しくなる!」という『横浜 謎解き散歩』から横浜を散歩したくなるエッセンスを横浜在住の僕がご紹介!
進化し続け、新スポットが続々とできる横浜。
今、話題のカジノ誘致。山下公園の先の山下ふ頭にできるとの噂ですが、どうなるんでしょうね?中華街も近いし盛り上がる事は間違いなし!
でも、その先には日本三大ドヤ街の寿町があります。コントラストの激しい横浜。5年後どうなっているかわからない、不思議な街。
文化、人種、ことば、カラフルな横浜。知ればもっと横浜が好きになる!早速、謎とき散歩、行ってみましょう!
読めば横浜観光が3倍楽しくなる!横浜の謎とき18選。
- 「ぺけ」「どんたく」などの言葉を産んだ「ハマことば」とは?
- 豚屋の火事が日本大通りを生んだ?
- 「カネの橋」と呼ばれた関内の吉田橋?
- 突堤「ゾウの鼻」はそもそもなぜ曲がっているの?
- 日本初の鉄道開通式から国旗掲揚が始まった?
- 初代、横浜駅は今の桜木町駅?
- レンタサイクル発祥は横浜、元町?
- 朽ち果てた謎のプラットフォーム「平沼駅」とは?
- 関内の由来と関外とは?
- 「横浜三名士」の名前を引き継ぐ高島町?
- 日本で最初にアイスクリームを製造して販売したのは馬車道?
- サンマと関係ないよ、サンマーメン。
- ナポリタンが生まれたホテルニューグランド?
- 戸塚で生まれた鎌倉ハム?
- 無料で人気の野毛山動物園は遊園地だった?
- FIFA公認のサッカーお守りが買える師岡熊野神社とは?
- 浦島伝説が今も残る慶雲寺とは?
- 夢が叶う横浜の3つの塔とは?
- 今回の本
「ぺけ」「どんたく」などの言葉を産んだ「ハマことば」とは?
1859年に開港した横浜。外国人居留地が設置され、様々な国の外国人と日本人との交流が生まれました。
その中で外国の言葉と日本語が混ざった独特の「横浜ことば」「ハマことば」なるものが誕生。
などなど。ペケという言葉は残念ながら、最近は聞かなくなっちゃいましたね。今こそ響きが可愛いので積極的に使いたい!
どんたくといえば「博多どんたく」。九州は長崎があるのでそちらで生まれた言葉かもしれませんが由来は一緒ですね。こちらは今後も盛り上がっていくでしょう!
ハマことばは他にも「ガクラン」「ちゃぶ台」「デマ」「ハイボール」「ランドセル」などなど。
ただし時代と共に消えていった「ハマことば」も多く寂しいですね。せっかく生まれた言葉たち、今後とも継承していきたいですね。
豚屋の火事が日本大通りを生んだ?
オシャレなカフェが並び、海へと続く気持ちの良い広々とした道路、日本大通り。こちらは豚屋の火事から出来たといいます。
1866年、横浜の開港場内の豚肉料理店から火災が発生。日本人移住区から燃え広がり外国人居留地にまで及ぶ大火事。
日本人移住区の約1/3、外国人居留地の約1/4が消失した豚屋の火事。
この火災を教訓に近代的な都市づくりに目覚め、「灯台の父」スコットランド人技師・リチャード・ヘンリー・ブラントンが設計した火災が拡大しない広々とした道路、日本大通りができました。
今でも大通りを見つめるようにR.H.ブラントン胸像が佇んでいます。

ベトナムフェスの時の日本大通り
日本大通り、散歩すると広々として海風が心地よく気持ちいいですよね!
週末はよくイベントもやっていますので、ぜひ散策してみてくださいね!
「カネの橋」と呼ばれた関内の吉田橋?
JR 関内駅北口の馬車道と伊勢佐木町の伊勢佐木モール関内側入口をつないでいる吉田橋。
横浜開港後の1860年ごろ、日本人が外国人を襲撃する事件が頻発しており、日本人が容易に外国人居留地に立ち入れないように関門を設置。
通行人と手荷物の検査を行うようになり、関門の海側を関内と呼ぶようになりました。
そして、この吉田橋の厳しい取り調べと通行料を取ることから、当時は珍しい鉄橋とかけて「カネの橋」と呼ばれるようになりました。
今はなんの変哲もない地味な橋で地下道の方が人気がありますが、当時はずいぶんにぎわっていたんですね。
しかし150年前まで日本人が外国人を刀で斬っていたというのがもはや想像しがたいですね。
突堤「ゾウの鼻」はそもそもなぜ曲がっているの?
象の鼻パークにある曲がった突堤、通称「ゾウの鼻」。そもそもなぜ曲がっているのでしょう?
1859年に開港した当時の横浜には、大型船が接岸できる港湾施設がありませんでした。
当時の下船方法は大型船が沖合に停泊、そこから乗客と船員は小舟に乗り移って突堤に上陸していました。
1866年、海からの風や波から小舟を守るために弓なりに湾曲した突堤が誕生。
その形状から「象の鼻」という愛称で呼ばれるようになりました。象の鼻は人々を海風や波から守ってくれてたんですね。心優しきゾウ!

ゾウノハナソフトクリーム
象の鼻パークにはかわいい象のオブジェや、ゾウの鼻テラスにはとってもキュートな「ゾウノハナソフトクリーム」が売っており、海の景色を楽しみながらゆったりとした優しい気持ちになれますよ!
日本初の鉄道開通式から国旗掲揚が始まった?
1872年、日本初の鉄道が新橋から横浜間に開業。当時、馬車で約4時間、駕籠(かご)で約10時間だった新橋-横浜間がたった54分に短縮されるという画期的なものでした。
日本の歴史上、初めての鉄道の開業に備え、横浜全体で祝うのに相応しいアイデアが募集されました。
協議の末、開通式に横浜のすべての家に国旗、日の丸、日の丸提灯をあげさせる事となりました。
無事、開業式も盛大に行われ、その後、政府は祝祭日に国旗を掲揚することを法律で正式に定めました。
鉄道は色んなものを繋げてくれますね!当時の日本人は何もかもが大きく変わる激動の時代でワクワクしてたでしょうね。
余談ですが、外務省HPによると世界で線路が長い国はアメリカの22万8218キロ。そしてロシア8万5266キロ、中国6万6989キロ。日本は2万140キロとの事。
やはりアメリカの鉄道はスケールがすごい!
これからも鉄道、色んなものを繋げてください!
初代、横浜駅は今の桜木町駅?
日本初の鉄道の発着駅は横浜駅。しかし JR 桜木町駅のそばに「鉄道発祥の地記念碑」があります。
それは1872年当初、日本で最初の鉄道開業時の横浜駅は現在の JR 桜木町駅の場所に建てられていたからです。

とある日の桜木町駅前
その約40年後の1915年に横浜駅は高島町に移転。今の横浜駅は三代目に当たります。しかし、いつになったら工事が終わるんでしょうね?
桜木町駅の周辺を調べてみると鉄道発祥にちなんだオブジェや展示物があちこちにあります。そして結構、分かりにくいところに「鉄道発祥の地記念碑」があります。探してみてください!
レンタサイクル発祥は横浜、元町?
激動の1860年以降、次々に交通革命も起きて自転車も海外から伝来。
この時、贅沢品だった自転車を購入し、石川孫左衛門が元町に貸し自転車屋を開業。好奇心旺盛の人々が開業と同時に殺到。高い料金に関わらず、行列ができるほどお店は繁盛しました。
今も横浜ではレンタサイクルの伝統が引き継がれています。
赤いレンタサイクルに乗って海風を感じながら横浜を散歩するのはとても気持ちが良いですよ!

赤いベイバイクでお散歩!
明治時代から進化したレンタサイクル“横浜コミュニティサイクル【baybikeベイバイク】”で街を探訪してはいかがでしょう!
朽ち果てた謎のプラットフォーム「平沼駅」とは?
京浜急行の横浜駅と戸部駅の間にある廃墟を思わせる朽ち果てたプラットフォーム。
電車の車窓からも見えるこの謎めいた朽ち果てたプラットフォームは戦前から戦中にかけて設けられた「平沼駅」の遺構。第二次世界大戦中のエネルギー不足で区間の短い駅を廃止することになり「平沼駅」は廃止。
廃駅になったもののモダンな造りの駅舎は取り壊されることもなく、そのまま残されていましたが 米軍による横浜大空襲によって駅舎は消失。焼けただれた状態の鉄骨とプラットフォームが残るのみの巨大な鳥かごのようになりました。
夜、この近辺を通るのはちょっと怖くて、この廃墟はなんなんだろう?とずっと不思議に思っていたのですがそんな秘密があったんですね。
今後この遺構がどうなるかは今のところ未定。横浜駅前の一等地なのでほったらかしはもったいなく思っちゃいます。
関内の由来と関外とは?
1858年の日米修好通商条約で当時、寒村だった今の横浜が開港場として選ばれました。
この時は神奈川の方が人の往来も多く賑わってたんですが、あえて寒村を選んだのは攘夷思想を持つ武士や郎人と外国人の接触によるトラブルを幕府が避けたかったためです。
さらに開港場の周囲を川で囲み、攘夷派の武士や浪人が開港場内に容易に入れないようにする徹底ぶり。全ての橋のたもとと渡船場に関門を設置しました。
関門で武士は刀を預け名前の申告が義務付けられていました。当時の人々は、いつしか関門の内側を関内、外を関外と呼ぶようになりました。つまり関内とは開港場です。
今は簡単に歩いて関内に入ることが出来ますが当時は立ち入りが厳しかったんですね。そうやって関内を見ると何やら当時の面影が残っている気がします。
関内は裏路地に隠れた店がたくさんあってきっとお気に入りの一店が見つかると思いますよ!一杯寄って行きませんか?
「横浜三名士」の名前を引き継ぐ高島町?
横浜には、「高島」と名前のつく地名や交通施設があります。これは明治時代初期に実業家として横浜の発展に多大な貢献を果たした高島嘉右衛門(たかしま かえもん)にちなんだもの。
明治初期に横浜港の埋め立て事業を手がけたことで横浜の発展に寄与しており、「横浜の父」あるいは吉田勘兵衛、苅部清兵衛らとともに「横浜三名士」ともいわれる。その業績は高島町という地名にも残っている。「高島易断書」を著す。
(引用・抜粋:ウィキペディア)
号は呑象(どんしょう)。引退後は易断によっても名をはせ、著作『高島易断』は翻訳されて海外の知識人達にも送られているほどです。占いと人生の成功、非常に興味があります。
『高島易断』を調べてみると今も高島易断を行い、本部と名乗る組織はいくつか東京などにあるようです。しかし残念な事に現在の横浜の高島町にその流れを組むところは無さそうです。
易聖と呼ばれた嘉右衛門は占いを学問と捉え、占いに従って事業も成功させたそうです。これは調べてみる価値がある!
近いうちに調べてまたブログでまとめたいと思います。
日本で最初にアイスクリームを製造して販売したのは馬車道?
1860年に遣米使節の一員としてアメリカに渡った町田房造。その際、船上で日本人として初めてアイスクリームを味わいました。
1869年に町田はその体験を活かして馬車道で氷水店を開店。氷水とともにアイスクリームを「あいすくりん」と名づけて売り出したものの値段が高く大赤字。現在の価値で8000円ほどしたそうです。
店をたたもうとも思ったそうですが、伊勢山皇大神宮の大祭で茶店を出してアイスクリームを販売したところ予想外の大盛況。これをきっかけに日本人にもアイスクリームが浸透しました。さすがは横浜のお伊勢さん、ご利益抜群ですね。
パワースポットの伊勢山皇大神宮も近いうちに調べようと思っています。
今でも馬車道には当時の味を再現した「横濱馬車道あいす」なんて店もあります。歴史を感じながらアイスクリームを食べてみてはいかがでしょう?
ちなみに馬車道と伊勢山皇大神宮は歩けない距離じゃないですが結構離れていますのでご注意ください。
サンマと関係ないよ、サンマーメン。
戦後の食糧難の時代に横浜で生まれた大衆食サンマーメン。もちろん魚のサンマは関係ありません。サンマーメンはあんかけ五目焼きそばの具の部分をラーメンの上に乗せたあんかけラーメンですね。
サンマーは漢字で「生馬麺」。広東語で「生=サン」は新鮮でシャキシャキしたという意味。「マー=馬」は上に乗せるという意味。諸説ありますが文字通り新鮮な野菜や肉を手早く炒めたシャキシャキ感のある具を麺の上に乗せることからサンマーと命名されたと言われています。

ヨコハマ名物サンマーメン
中華街にある聘珍樓(へいちんろう)が発祥の店と呼ばれていますが、こちらもいくつか発祥を、名乗る店があるようです。いつも行列が出来ているサンマーメン発祥の店。
立ち寄った際には、せっかくなので召し上がってみてください。あんが熱々なのでヤケドにはご注意!
僕は店の雰囲気ひっくるめてサンマーメン発祥の店のひとつと呼ばれる「玉泉亭」が好きです。
ナポリタンが生まれたホテルニューグランド?
関東大震災の横浜の復興のシンボルとして開業したホテルニューグランド。
初代総料理長のスイス人サリー・ワイルは日本の近代フランス料理の父と呼ばれる料理人。ナポリタンはその精神を継承した二代目総料理長、入江茂忠が開発。
元々、塩とトマトケチャップの味気のない米軍の軍用食があり、そこから創作。ハム、マッシュルーム、タマネギ、ニンニクを加えて茹でたあと12時間さましたスパゲッティと絡め、見事、新メニューに。
ナポリの屋台で売られていたトマトのパスタに因んで命名。ホテルニューグランドでは「ドリア」「ナポリタン」「プリンアラモード」の3つの料理の発祥の場所とされています。もちろん現在でも食べることが可能。
お値段はそれなりですが、あえて立派なホテルでナポリタンを注文するのが余裕のある大人というもの。僕はまだ注文する勇気がありませんが、ぜひ歴史の味をご堪能下さいね!
戸塚で生まれた鎌倉ハム?
「鎌倉ハム」というハムのブランド名から、現在の鎌倉市で誕生したハムを連想しますが、実は今の横浜市戸塚区柏尾町で明治時代初期に製造されたハムとなります。
明治時代初期、横浜の外国人居留地で食肉店「ホワイト・ホース・ファーム・ブッチャリー」を経営するなど食肉業を営んでいたイギリス人ウィリアム・カーティスが、神奈川県鎌倉郡下柏尾村に外国人向けの簡易ホテルを建て、「白馬亭」あるいは「馬の首ホテル」と命名し、その経営に乗り出しました。
カーティスはホテルで、日本で初めてハムの製造を開始。ホテルの裏手には養豚場も設けられてあったそうです。
その数年後、近隣に在住していた益田直蔵、斎藤満平などが、ハムのつくり方をカーティスから学び、ハムを製造するようになりました。これら一連の場所が、現在の横浜市戸塚区柏尾町。しかし、当時は神奈川県鎌倉郡下柏尾村だったので「鎌倉ハム」となり、全国にその名を知られているようです。
今も伝統が引き継がれ、現在の「鎌倉ハム」の主な業者は以下の通り。
<鎌倉ハムの主業者>
・鎌倉ハム(名古屋市) – 齋藤系
・鎌倉ハム富岡商会(鎌倉市)
・鎌倉ハム 石井商会(横浜市南区) – 益田系
・鎌倉ハム村井商会(横浜市瀬谷区)
・鎌倉ハムクラウン商会(横浜市磯子区)
・鎌倉ハム鎌倉クラシコ(熊谷市)(引用・抜粋:ウィキペディア)
よく見ると今は鎌倉市でハムを作っているのは1社だけのようですね。
歴史を感じる鎌倉ハム。特別な製法があるかどうかはわかりませんが他のハムより美味しく感じますよね。ブランドイメージのおかげでしょうか?
とにかく「鎌倉」って付くだけでなんでもありがたく感じます!
無料で人気の野毛山動物園は遊園地だった?
JR桜木町駅や京浜急行本線日ノ出町駅から徒歩約15分の野毛山動物園。ライオンなど90種類近くの動物たちが入場料無料で見る事が出来て大人気。素敵な場所ですよね。昔ながらの動物園の雰囲気もたまりません。

野毛山動物園のトラ
現在は動物園のイメージが強い野毛山ですが、昔は横浜の海を見渡す高級住宅地として庶民の羨望を集めていました。しかし1923年の関東大震災で豪邸の数々が崩壊。跡地には市民の憩いの場、及び避難所として野毛山公園ができました。
1949年、野毛山公園は日本貿易博覧会の会場に選ばれ、動物を約3ヶ月展示したところ大好評。そこで博覧会の閉会後、日本庭園のエリアに動物園、洋式庭園のエリアに遊園地を新設。
昭和26年4月、動物園と遊園地をかねそろえた新スポット野毛山遊園地ができました。
昭和39年、近代水道発祥の地でもある野毛山の水道排水地の整備に伴い、遊園地が閉鎖され公園に生まれ変わりました。
それを機に遊園地の入園料は無料。今でもその方針が貫かれています。いつまでも無料の遊園地、ずっと続いてほしいですね。

はま子像がお出迎え!
昔は、平成15年10月に死亡するまで50年以上にわたって人気者のインド象のはま子もいたんですよ。今はゾウはいませんが、動物園の入口でゾウが像になって、今もお客さんを見守っています。
僕のいやし、野毛山動物園!ゆっくりしていってね!
FIFA公認のサッカーお守りが買える師岡熊野神社とは?
2002年、日韓合同で開催されたFIFA ワールドカップのメイン会場に選ばれたのが港北区の横浜国際総合競技場。そして競技場と同じ港北区に「師岡熊野神社」があります。
724年の創業以来、長く関東地方を守り続けてきた師岡熊野神社。ここの御社紋は古来より「八咫烏」(やたがらす)。これは日本公式ユニフォームのエンブレムと同じ。
八咫烏は太陽を象徴しており熊野の神の使いとされる三本足の大きな鳥。
同じ港北区の師岡熊野神社の御社紋が八咫烏であることにサッカーファンが気づき、それから、チームの必勝と選手の健康を祈って多くのサッカー関係者が訪れるようになりました。
ここでは日本サッカー協会公認のサッカー御守が購入できます。ホームページでも購入できますよ。サッカー好きは一度行ってみる価値あり!
浦島伝説が今も残る慶雲寺とは?
横浜開港時にフランス領事館として利用された慶雲寺。室町時代の永楽年間の創建という浄土宗の寺院。京浜急行本線神奈川駅と仲木戸駅の間の線路の西側、神奈川区の滝の川沿いに位置し、浦島太郎ゆかりの浦島寺としても知られています。
ここは浦島太郎が竜宮城から持ち帰ったという浦島観音菩薩像が本尊として安置され現在も浦島像や乙姫像、亀の台座など佇まいが残っています。

慶運寺の浦島と乙姫像
全国各地にある浦島伝説。慶雲寺のホームページによると、「一番信憑性が高い」と仰っています。果たしてここが浦島伝説発祥の地なのか?足を運んでご自分で判断してみてください。
僕はずっと、亀をいじめている子供たちを探しているんですがどこにいるかご存知の方いらっしゃいませんか?
夢が叶う横浜の3つの塔とは?
横浜三塔と称される戦前に建てがられた3つの歴史的建築物、「神奈川県庁本庁舎」、「横浜税関本関庁舎」、「横浜市開港記念会館」。それぞれトランプのカードあるいはチェスの駒に例えた名称がつけられています。

横浜税関から見たクイーン
この三塔を1日ですべて巡ると願いが叶うという都市伝説があります。
由来は海外の船乗り達が三塔に航海の安全を祈願したという噂もあるが出所は不明。
三塔が同時に見渡せるスポットもありますよ。
<三塔が見渡せるスポット>
たびたびテレビに取り上げられている噂のパワースポット。三塔を巡れば夢が叶うかも!信じるか信じないかはあなた次第です!
今回の本
【書籍名】横浜 謎解き散歩
【著者名】小市和雄
【出版社】中経出版
【出版日】2013年9月8日
僕は横浜に住んで約10年、詳しいと思っていましたがまだまだ知らない事だらけ!開港する約150年前の横浜は深い歴史があるのかまだ若い街なのかはよくわかりませんが、これだけダイナミックに変化して魅力的な街はそれほどないと思います。
この本を読んでますます横浜が好きになりました。そしてもっと謎を探して散歩しようと思いました。
この本には他にも「崎陽軒のシウマイ」「山手公園」「ペンキ発祥」「横浜マリンタワー」の謎など今回紹介しきれなかった横浜の面白い謎がたくさんあります。興味のある方はぜひ手に取ってくださいね!
今後も、もっと横浜の情報を僕から発信したいと思いますので今後もこのブログをよろしくお願いします!
そろそろテコ入れする予定ですが、横浜をリーズナブルに楽しめる記事もまとめてあるので興味のある方は一緒に読んでくださいね!
よろしくお願いします!
ランキング参加しています。お願いします!
![]() 一緒にブログをやりませんか?ブログをやるならエックスサーバ!
一緒にブログをやりませんか?ブログをやるならエックスサーバ!![]() どんどん人生は良くなります。頑張りましょう!
どんどん人生は良くなります。頑張りましょう!
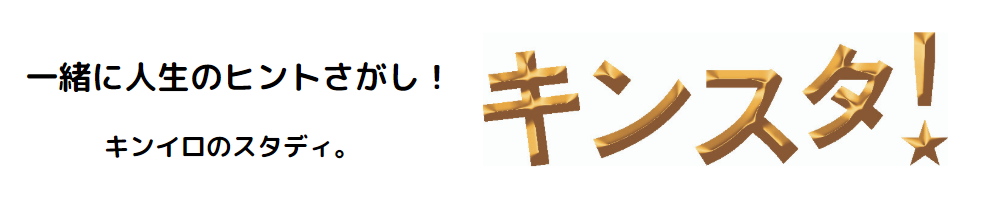
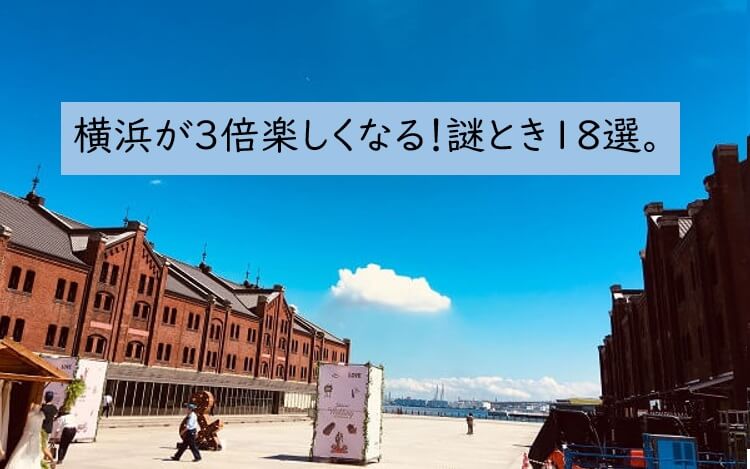



コメント